現在日本は議院内閣制を取っており、政党内閣が組織されるのが当たり前になっています。
ですが、日本で政党内閣が誕生したのは20世紀になってからであり、まだまだ新しい制度です。しかも途中から政党内閣制はくずれていました。
有権者のひとりとして政治に適切にかかわれるようになるため、現代日本の政治の根幹である政党内閣についてくわしく知りたいと思います。
※関連記事:内閣不信任決議とは:不信任決議が可決された日本の歴代内閣4つとその経緯を紹介
政党内閣とは
政党内閣とは、議会における多数派政党、または複数の政党が連立して形成する内閣のことを指します。
政党内閣は「議会の信任」を基盤として運営されるため、議院内閣制や議会制民主主義と密接に関係しています。政党内閣では、内閣の構成メンバーが特定の政党に所属しており、その政党の政策理念や方針に基づいて政治が行われます。
議会制民主主義については以下の記事で詳しく解説しています。
議会制民主主義とは:議会制民主主義の仕組みやメリット・デメリットと今後の展望を解説
政党内閣の主な特徴
議会との密接な関係
- 内閣は議会の信任を得る必要があるため、与党(または連立与党)が主導権を握ります。
- 議会の多数派であることが政党内閣の条件であり、与党が議会運営や政策決定をリードします。
政策の一貫性
政党内閣では、特定政党のマニフェストや政策理念に基づいた一貫性のある政策が実施されやすいです。
政策の決め方については以下の記事で詳しく解説しています。
政策とは?その決め方と影響、目的と重要性、歴代総理の代表的な政策例を紹介
内閣不信任案のリスク
議会で多数を失った場合、衆議院で内閣不信任案が可決されることで内閣総辞職や議会解散が求められる場合があります。
内閣不信任決議については以下の記事で詳しく解説しています。
内閣不信任決議とは?わかりやすく解説!衆議院解散の理由:不信任決議が可決された歴代内閣4つを紹介
日本における政党内閣の歴史
日本初の政党内閣は大隈重信内閣
日本ではじめての政党内閣は1898年の第一次大隈重信内閣でした。
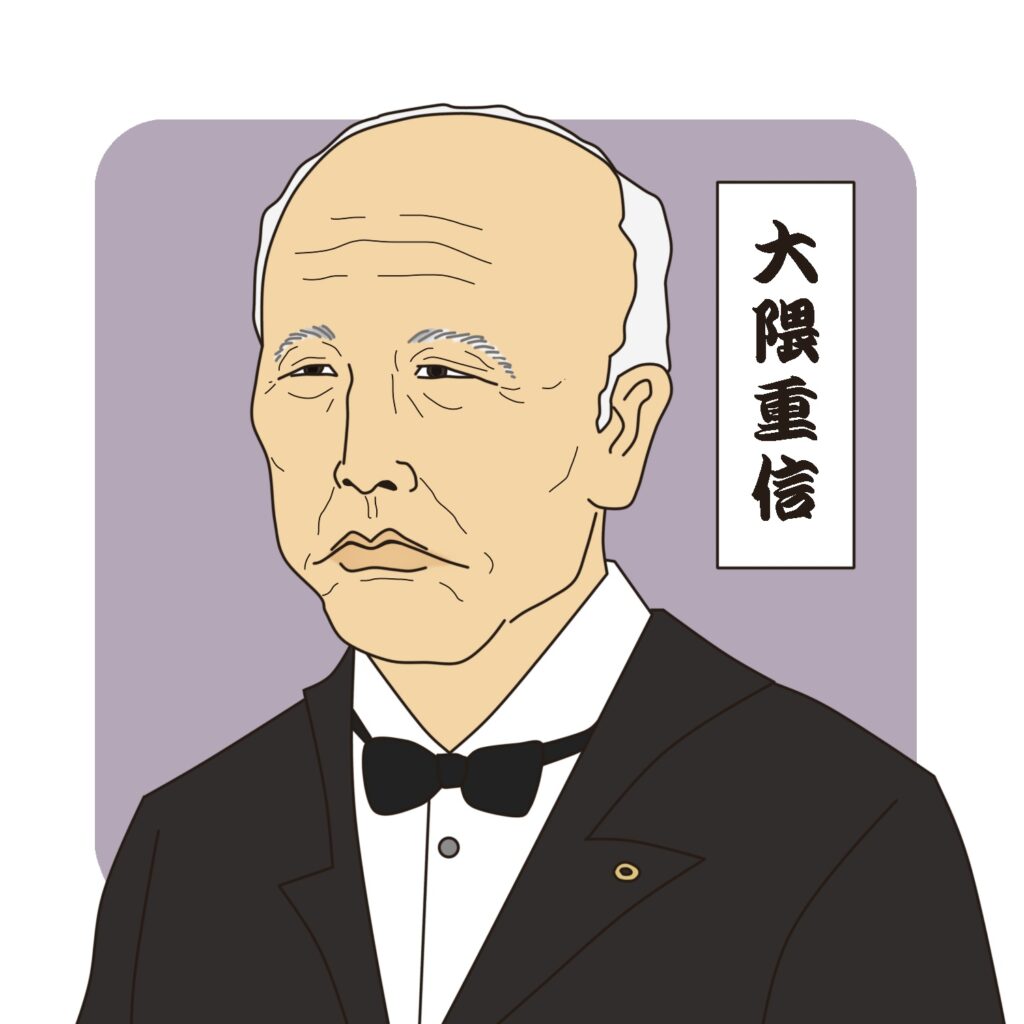
この頃は長州藩や薩摩藩出身者が主導権をにぎる藩閥政治が当たり前でした。こうした体制に反発して自由党と進歩党が協力して与党・憲政党となり、憲政党の議員を中心に大隈重信が内閣を組織します。
どちらの党の議員が重要閣僚ポストに就くかでモメにモメ、内部分裂ばかりします。結局、132日で辞職しました。
なお、大隈重信については以下の記事で詳しく解説しています。
内閣総理大臣・大隈重信の生涯と業績:早稲田大学創設や政治家としての足跡を生い立ちから解説
本格的な政党内閣誕生:原敬内閣の成立(立憲政友会)
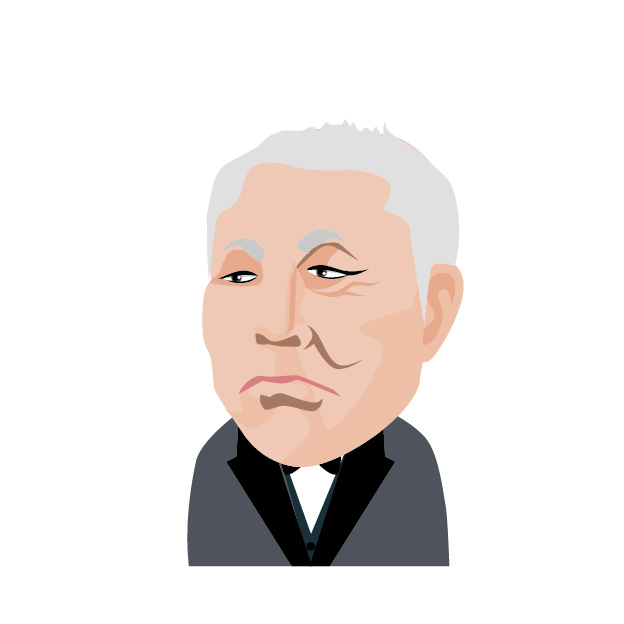
政党内閣は日本の近代政治において画期的な転換点となりました。その起点となったのが1918年に成立した原敬内閣です。それまでの日本は藩閥政治が主流であり、薩摩藩や長州藩出身の政治家が権力を独占していました。しかし、日清戦争や日露戦争後、都市化や産業化が進み、国民の政治参加への期待が高まります。原敬は立憲政友会を基盤とする内閣を組織し、藩閥ではない初の本格的な政党内閣を成立させました。彼の内閣は、国民の支持を背景に、都市のインフラ整備や教育制度の充実を進め、日本政治の民主化に寄与しました。
なお、原敬については以下の記事でくわしく解説しています。
内閣総理大臣・原敬とは何した人か?日本初の政党内閣・平民宰相としての業績と暗殺の経緯を振り返ります
国勢調査をはじめて実施したのも原敬内閣
実は原敬内閣は、「初の本格的な政党内閣」というだけでなく、「初の国勢調査を実施した内閣」でもあります(総務省統計局より)。
第一次世界大戦が勃発しており、戦時体制を取るために日本国内の状況を正確に把握するためだったようです。
立憲政友会のその後
立憲政友会は、明治時代末期に設立された日本の主要な保守的な政党の一つで、当初は藩閥政治に対抗するための政党として形成されました。
原敬内閣が成立した1918年、立憲政友会は日本の政治において強い影響力を持つ政党であり、政党内閣の誕生を象徴する存在となりました。
立憲政友会は、戦前の日本政治において長期間支配的な地位を占めましたが、戦後の日本にはその影響力を持ち込むことはできませんでした。第二次世界大戦後、日本の政党政治は大きな変革を迎え、立憲政友会は解党され、後に新たな保守的な政党である自由党や自民党が台頭することになります。
そのため、立憲政友会は戦後の日本政治においては直接的な影響を及ぼしませんでしたが、政党内閣の実現を意味する原敬内閣の誕生は日本の政党政治の重要な転機を示しています。
関東大震災で政党内閣は一時途切れる
原敬内閣以降も政党内閣はつづきますが、1923年に途切れます。この年に関東大震災が起こったためです。
大震災の被害は大きく、国を挙げて対応するため西園寺公望が山本権兵衛を総理大臣に任命します(当時は総理大臣の決定方法に明確な規定がありませんでした)。震災後の不況により政党内閣への不満も大きくなっていきました。
山本内閣は普通選挙の実現に向けても動きますが、皇族が共産主義者の難波大助に襲撃されて負傷したのを機に辞表を提出。襲われた皇族含め周囲が慰留しますが、128日で総辞職となりました。
なお、山本権兵衛については以下の記事でくわしく解説しています。
内閣総理大臣・山本権兵衛の生涯と業績:軍部大臣現役武官制の廃止に尽力した軍人政治家の功績
普通選挙については、1925年の加藤高明内閣で一応実現します。加藤高明については以下の記事で詳しく解説しています。
加藤高明とは何をした人物?治安維持法と普通選挙法の制定で知られる総理大臣の功績を解説
五・一五事件以降は政党内閣がない
1932年、満州国樹立を目指す軍部の動きを抑制しようとしていた犬養毅首相や政友会本部が襲撃されます(五・一五事件)。
当時、軍部系の大臣には軍部から推薦した現役の軍人が就任するという決まりがありました(軍部大臣現役武官制)。
この制度をタテに軍部は自分たちに批判的・抑制的な内閣には大臣を推薦しなくなります。
五・一五事件については以下の記事で詳しく解説しています。
五・一五事件とは?犬養毅暗殺から二・二六事件への影響まで詳しく解説:なぜ起きたのか、事件後の日本社会
二・二六事件以降はこの傾向が強まり、さらに大政翼賛会に統合されて太平洋戦争へとつながりました。
結果的に、犬養毅内閣が戦前で最後の政党内閣となりました。
なお、二・二六事件については以下の記事で詳しく解説しています。
二・二六事件の真相と影響: 日本政治を揺るがした皇道派・青年将校の反乱はなぜ起きたのか
政党内閣が日本政治に与えた影響
政党内閣の成立は、日本の政治文化を大きく変えました。藩閥政治から脱却し、国民の意思が反映される政治への第一歩を踏み出したのです。
しかし一方で、政党内閣は派閥や利益団体との癒着が生じやすく、短命に終わるケースも少なくありませんでした。
それでも、議会を通じた政策決定が進展し、日本の近代政治体制の基盤を築くことに成功しました。
戦後の政党内閣の展開:吉田茂や池田勇人内閣
戦後の日本では、戦前に軍部主導で失われた政党内閣が復活しました。その先駆けとなったのが1946年の吉田茂内閣です。
吉田茂は、戦後復興のための基盤整備と外交政策に重点を置き、特にアメリカとの協調を進めました。
また、池田勇人内閣は1960年代に「所得倍増計画」を掲げ、経済成長を目指しました。
これにより日本は高度経済成長を遂げ、国民生活の向上が実現しました。戦後の政党内閣は、政策を実行する力強いリーダーシップを発揮し、戦前とは異なる形で政治の安定化に寄与しました。
内閣総理大臣のリーダーシップについては以下の記事で詳しく解説しています。
内閣総理大臣の役割とリーダーシップ:長期政権と短命政権の違いを実例をまじえて解説
近年の政党内閣とその特徴:自民党政権の長期化
近年の日本政治では、自民党が政党内閣の主導権を握り続けています。特に小泉純一郎内閣や第二次安倍晋三内閣では、長期政権が特徴でした。
一方で、1990年代以降は非自民勢力による連立政権も見られ、政治の多様化が進みました。
連立政権は妥協が必要となるため、政策決定が遅れる場合がありますが、安定した与党運営が可能な場合もあります。
短命内閣が続いた時期もあり、政治不信が広がった反面、自民党の安定的な基盤が再び注目される時期も見られました。
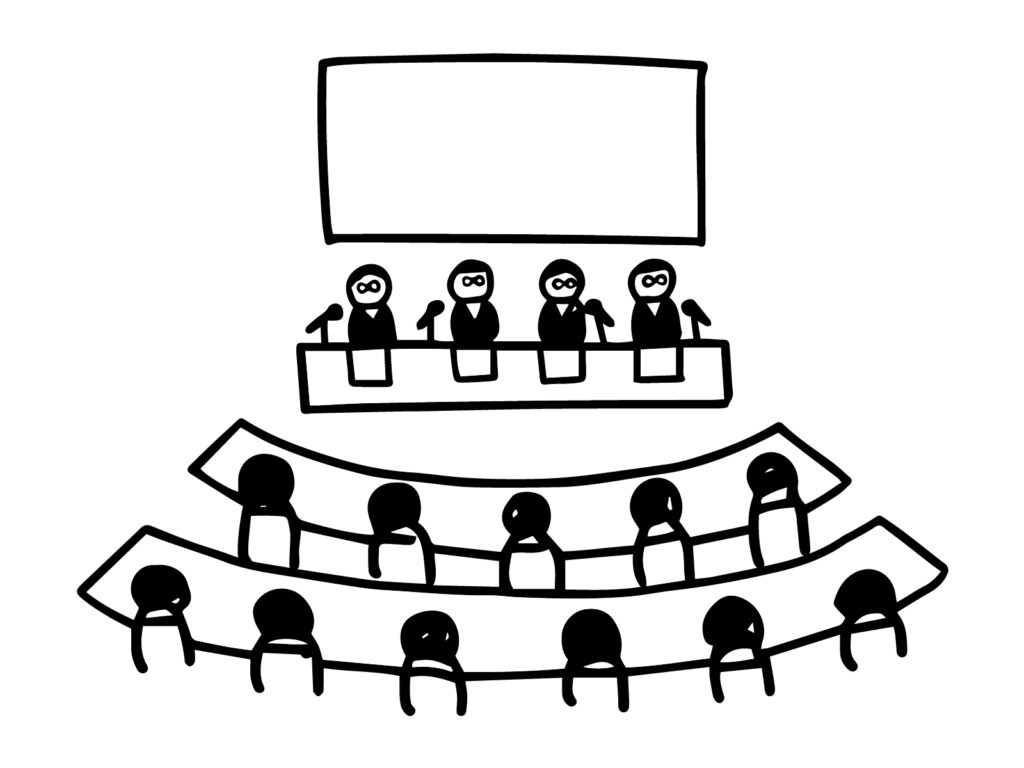
日本の政党内閣の歴史年表
明治時代:藩閥政治から政党内閣へ
- 1868年 – 明治維新により近代国家の基礎が築かれる。藩閥(薩摩藩・長州藩)出身の政治家が主導権を握る。
- 1885年 – 内閣制度が発足。初代内閣総理大臣は伊藤博文(藩閥政治の代表)。
- 1890年 – 帝国議会開設。政党が徐々に政治に影響を持つようになる。
- 1918年 – 原敬内閣が成立。日本初の本格的な政党内閣(立憲政友会が中心)。
大正時代:政党政治の進展
- 1924年 – 第二次護憲運動の結果、加藤高明内閣が成立。以後、政党内閣が主流となる。
- 1927年 – 田中義一内閣が成立。藩閥勢力が一時的に復活するも、政党内閣の流れは続く。
- 1932年 – 五・一五事件で犬養毅首相が暗殺され、軍部の影響が強まる。
昭和時代(戦前):政党政治の終焉
- 1937年 – 第一次近衛文麿内閣成立。軍部主導の内閣が台頭し、政党内閣は事実上終了。
- 1940年 – 大政翼賛会が設立され、政党が解散。
昭和時代(戦後):政党内閣の復活
- 1946年 – 吉田茂内閣成立(日本自由党)。戦後初の政党内閣。
- 1955年 – 55年体制成立。自由民主党が与党となり、長期的に政党内閣を主導。
平成時代:連立政権の時代
- 1993年 – 自民党が下野。細川護熙内閣が成立(非自民・非共産の連立政権)。
- 1994年 – 村山富市内閣成立。戦後初の社会党出身首相。
- 1996年 – 橋本龍太郎内閣成立。自民党中心の政党内閣に戻る。
平成から令和時代:政党内閣の継続
- 2001年 – 小泉純一郎内閣成立。構造改革を掲げた長期政権。
- 2009年 – 民主党が政権交代を実現。鳩山由紀夫内閣成立。
- 2012年 – 自民党が政権奪還。第二次安倍晋三内閣成立(長期政権)。
- 2024年 – 石破茂内閣成立。現在も自民党が与党の政党内閣体制を維持。
政党内閣の特徴と他の政治体制との比較
現在の日本は政党内閣ですが、過去には異なる政治体制を採用していた時期もありました。政党内閣とほかの政治体制と比較してみます。
政党内閣の特徴:議院内閣制との関係性
政党内閣は議院内閣制の下で機能する政治体制の一部です。議院内閣制では、内閣が議会の信任を基盤として成立します。与党は議会多数派を形成し、政府運営の中枢を担います。
具体例として、与党が法案提出や政策実行を進め、野党が政府を監視・批判する役割を果たします。
この仕組みは政策決定が迅速に進む一方、与党が独占的な立場になる可能性も秘めています。
与党や野党の役割については以下の記事で詳しく解説しています。
与党とは?その定義と役割、政策決定プロセス、政権交代の歴史的経緯、野党との違いを徹底解説
野党とは何か?与党との違いと役割、そして重要性をデータを使ってわかりやすく解説
官僚内閣との違い

官僚主導の政治体制では、行政官が政策立案の中心を担い、政党の影響は限定的になります。一方、政党内閣は選挙を通じた国民の意思が反映されやすいという特徴があります。
ただし、政党内閣は派閥争いや利益団体との結びつきが課題となる場合があります。政策決定プロセスの透明性や責任追及の明確化が求められる点も異なります。
なお、国民の意思は選挙以外にも世論にも反映されています。世論について以下の記事で詳しく解説しています。
世論とは何か?その役割や政策に与える影響力、形成されるプロセスと調査方法をくわしく解説
大統領制との違い
大統領制では、大統領が行政の最高責任者として強い権限を持つ一方、議会と大統領が独立して存在します。議院内閣制の政党内閣は、議会と政府が連動して政策を決定するため、スピーディーな意思決定が可能です。
一方、大統領制は分権が進んでおり、権力の集中を防ぐ仕組みがあります。日本の政党内閣では、議会の信任が大きな役割を果たしている点が特徴です。

※関連記事:首相と大統領の違い:日本の内閣総理大臣の権限はどこまである?首相と大統領はどちらが良い政治をできる?
政党内閣のメリットとデメリット
政党内閣のメリットは?
政党内閣の最大のメリットは、与党が安定した政策運営を行える点です。国民の支持を受けた政党が議会の多数派を形成することで、法案の成立や政策の実行がスムーズに進みます。
また、選挙を通じて国民の意思を直接反映させるため、民主的な運営が期待されます。
与党による安定した政権運営
政党内閣のデメリット
一方で、政党内閣には短命内閣が発生しやすいというデメリットがあります。特に、派閥間の争いや連立政権の不安定さが原因となり、政策の一貫性が失われる場合があります。
また、長期政権が続くと、既得権益が温存されるなどの問題が生じる可能性があります。
短命内閣
派閥争い
既得権益の温存
なお、政治派閥については以下の記事で詳しく解説しています。
政治派閥とは:派閥のメリット・デメリットや無派閥との違いを解説し、派閥の歴史を振り返ります
現代における政党内閣の課題と展望
連立政権の課題と今後の可能性
日本では、政党間の連立が一般的になりつつあります。連立政権は、妥協を重ねて政策を進める必要があるため、決定が遅れることがあります。
しかし、多様な意見を反映するメリットもあります。今後、政策決定の迅速化と透明性の確保が求められます。

政党内閣が抱える今後の課題
国際化が進む中で、日本の政党内閣はグローバルな視点で政策を立案する必要があります。また、若者の政治参加が低下していることも課題の一つです。
選挙制度や教育を通じて、次世代の政治参加を促す仕組みを構築する必要があります。

若者の投票率については以下の記事で詳しく解説しています。
若者の選挙の投票率推移:投票率の変化と内閣支持率・政党支持率の関係について
政党内閣に関するQ&A
Q1. 政党内閣が初めて誕生したのはいつですか?
A. 1918年、原敬内閣が日本初の本格的な政党内閣として成立しました。
Q2. 原敬内閣はどのような役割を果たしましたか?
A. 都市インフラの整備や教育制度の充実を進め、国民の意思を反映する民主的な政治への第一歩を築きました。
Q3. 戦後の政党内閣で注目すべき内閣は?
A. 吉田茂内閣と池田勇人内閣が挙げられます。吉田茂は戦後復興、池田勇人は「所得倍増計画」を推進しました。
Q4. 自民党政権の長期化の背景には何がありますか?
A. 自民党が安定した議会多数派を維持したことに加え、連立政権の形成や政策の実行力が要因です。
Q5. 政党内閣と議院内閣制の関係性は何ですか?
A. 政党内閣は議院内閣制の下で、議会多数派を形成する政党が内閣を組織し、政策決定を進めます。
Q6. 官僚内閣と政党内閣の違いは何ですか?
A. 官僚内閣は行政官が政策立案を主導するのに対し、政党内閣は国民の支持を得た政党が中心となります。
Q7. 大統領制と政党内閣はどのように異なりますか?
A. 大統領制では大統領と議会が独立して存在しますが、政党内閣は議会と内閣が連動し、政策決定が迅速です。
Q8. 政党内閣の主なメリットは何ですか?
A. 与党が安定した政策運営を行いやすく、国民の意思を直接反映する仕組みが整っています。
Q9. 政党内閣が抱えるデメリットは何ですか?
A. 短命内閣が発生しやすく、派閥争いや長期政権の既得権益温存などの問題が挙げられます。
Q10. 日本の連立政権が抱える課題は何ですか?
A. 政策決定の遅れや妥協の必要性が課題ですが、多様な意見を反映する可能性も秘めています。
Q11. 政党内閣の今後の展望は何ですか?
A. グローバルな視点での政策立案と、若者の政治参加を促進する仕組み作りが重要とされています。
Q12. 若者の政治参加を増やすにはどうすればいいですか?
A. 教育や選挙制度の改善を通じて、政治に対する関心を高めることが求められます。
まとめ
政党内閣について説明し、日本における政党内閣の歴史を振り返りました。
日本初の政党内閣は1898年の大隈内閣で、本格的な政党内閣としては1918年の原敬内閣が初でした。
その後、五一五事件や二二六事件をとおして軍部が暴走しはじめて挙国一致内閣へと変貌していきます。戦後、吉田首相から政党内閣は復活し現在に至ります。
政党内閣について理解を深め、今後の投票活動にプラスにしていきましょう!
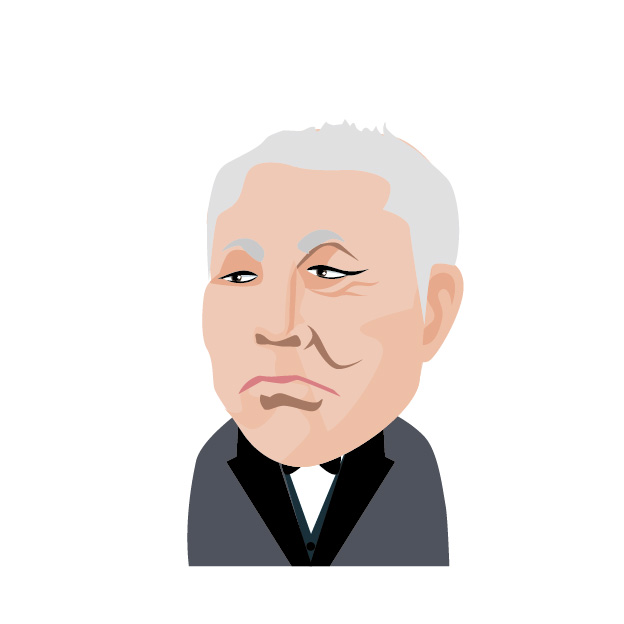


コメント