日本国憲法は、1947年に施行され、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三原則を基盤としています。これらの原則は、戦後の日本が直面した歴史的な背景と国際的な影響を反映しています。
本記事では、これら三原則の概要と、国際人権規約との関連、現代における課題を探ります。また、平和主義に関する海外の憲法との比較を通じて、日本の独自性を確認してみます。
日本国憲法の三原則
日本国憲法では、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の三つの基本原則が規定されています。
以下、その内容をくわしく解説します。
国民主権とは
「国民主権」とは、国の主権が国民にあることを意味します。これは日本国憲法の根幹となる理念で、具体的には憲法第1条と前文に記されています。
主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国憲法前文より引用
このように、国民が国政を担う主体であることを明示しています。
戦前の「天皇主権」との違い
「国民主権」は、戦前の「天皇主権」とは根本的に異なります。
明治憲法(大日本帝国憲法)では、天皇が「統治権を総攬する」とされ、天皇が最高の統治権者である「天皇主権」体制が敷かれていました。
明治憲法の第4条には、天皇が「大日本帝国ノ統治権ヲ総攬ス」とあり、天皇が立法、行政、司法のすべてにおいて最終的な権限を持つとされていました。
戦後の日本国憲法はこれを改め、主権者として国民を置き、天皇は「象徴」として国政に関わらない立場となりました。これにより、民主主義に基づく政治体制が確立されました。
国民主権の意義
この国民主権の理念は、戦後日本が民主主義国家として再建される重要な土台となりました。戦後の民主主義体制のもと、国民は選挙や国会を通じて国家の意思決定に直接参加できる権利を持ちます。
また、国民の意思が反映される代表民主制がとられ、国民による政治の実現が進められています。
※関連記事:議会制民主主義とは:議会制民主主義の仕組みやメリット・デメリットと今後の展望を解説
基本的人権の尊重とは
「基本的人権の尊重」は日本国憲法の三大原則の一つで、憲法が個々の人間の尊厳と人権を大切にし、国家によって侵害されない権利を保護することを意味します。
この考えは、国民主権や平和主義とともに、憲法の根幹をなす重要な柱です。
日本国憲法第十一条には以下のように規定されています。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第十一条より引用
このように、人権は「侵すことのできない永久の権利」として保障されています。
基本的人権の5つの権利
基本的人権はさらに、以下の5つの権利に分類されます。
それぞれ解説します。
自由権
自由権は、国家からの干渉や制約を受けずに、自由に行動や意見表明ができる権利です。これには、思想・良心の自由(第19条)、表現の自由(第21条)、身体の自由(第31~40条)などが含まれます。
自由権は主に、個人の精神的、身体的な自由を国家が制限できないという意味で、「国家からの自由」として捉えられます。
平等権
平等権は、すべての人が法の下で平等であり、差別なく扱われる権利です。憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって、政治的、経済的または社会的関係において差別されない」と明記し、法の下での平等を保障しています。
社会権
社会権は、個人が人間らしい生活を営むために、国家からの積極的な保護を受ける権利で、「国家による自由」とも言われます。これには、生存権(第25条)、教育を受ける権利(第26条)、労働基本権(第27~28条)などが含まれます。
社会権は20世紀になって発展した権利で、特に福祉国家の実現に向けた基本的な権利です。
基本的人権を守るための権利
自由権・平等権・社会権といった基本的人権が侵害されないよう、制度や仕組みで守られるべき権利もあります。それを基本的人権を守るための権利と言います。具体的には、以下のような権利です。
請願権:国民が政府や公共機関に対して、自らの意見や不満を表明し、特定の措置を求める権利です(憲法第16条)。この権利により、国民は自分の権利や利益が不当に侵害された場合、政府に対して正式に意見や改善要求を提出することができます。
裁判を受ける権利:基本的人権が侵害された場合に、その救済を求めて裁判を受ける権利(憲法第32条)です。これにより、すべての人は公平な裁判を通じて、権利侵害を正す機会が保障されています。
国家賠償請求権:公務員の不当な行為などによって権利が侵害された場合、国や地方公共団体に対して損害賠償を求めることができる権利です(憲法第17条)。これにより、公務員の不適切な行為から国民を守り、基本的人権の保障が強化されています。
人権擁護制度:人権侵害や差別に対する救済を提供する制度や組織も含まれます。具体的には、人権擁護機関やオンブズマン制度が設けられ、人権の擁護と救済が行われています。
新しい人権
現代の社会の変化に伴い、「基本的人権」に加えて新しい人権概念が登場しています。これには、個人の権利を守るために、技術や生活環境の変化に応じた新しい法的保護が求められています。
具体的には以下のような権利が新しい権利です。
プライバシーの権利:個人情報や私生活が不当に侵害されない権利です。特に、インターネットやSNSの普及に伴い、個人情報保護法や各種ガイドラインが整備されています。
環境権:健全な環境で生活するための権利であり、自然保護や公害防止のための取り組みの基礎です。裁判においても、環境保護が「人権」として認められるケースが増えています。
知る権利:政府や企業が持つ情報にアクセスできる権利です。情報公開制度の整備によって、国民は政策決定過程への透明性や説明責任を求めることが可能となっています。
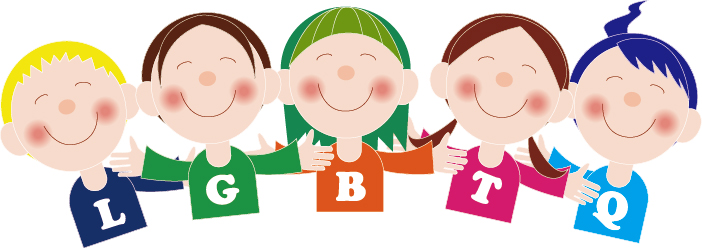
国際人権規約との関連
日本国憲法における基本的人権は、国際人権規約(1966年採択)とも深く関連しています。
この規約は、「経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約」(ICESCR)と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)の2つから構成され、加盟国に対して広範な人権の尊重を求めています。
日本は1979年にこれを批准し、国内法における人権保護をさらに強化しました。国際人権規約は、自由権や平等権の基本的な概念を補強するだけでなく、社会権についても重要な基準を提供しています。
基本三原則成立の歴史的背景
日本国憲法の三原則である「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」は、戦後の日本社会にとって重要な意義を持っています。
この三原則の成立には、日本の戦前の歴史と、戦後の国際環境が大きく影響しています。
以下に、それぞれの三原則がどのような歴史的背景から導入されたのか解説します。
国民主権の成立
戦前の日本は「大日本帝国憲法」の下で「天皇主権」を基盤としていました。国家の最高権力は天皇にありました。
しかし、天皇が軍部の最高責任者であるという規定のもと、軍部の暴走を招く結果になりました。
そのため、第二次世界大戦終結後、連合国は日本の民主化を目指し、憲法改正を通じて国民が主権を持つ体制の確立を求めました。1946年に公布された日本国憲法では、第1条で「主権は国民に存する」と規定されました。
ここに至って、国民が自らの意思で政治を決定する民主的な原則が導入されるのでした。

基本的人権の尊重の導入
戦前の日本では、個人の人権が充分に保障されていたとは言えませんでした。例えば、治安維持法のような法律により、政府が言論や思想を取り締まることが可能でした。国民は自由な意見の表明が制限され、違反すると連行され拷問を受けることもありました。
これが一部の権力者の暴走につながった一因とされています。
そこで戦後の憲法では、「人権が不可侵であり、国家によって奪われることのない普遍的な権利である」と定められました。これには、戦後の国際社会での「人権」の重要性が影響しており、特に国際連合憲章や世界人権宣言の理念が反映されています。
平和主義の価値観確立
日本が第二次世界大戦で敗戦したことは、日本の「戦争放棄」と「非武装平和主義」という新しい価値観を確立する大きな契機となりました。
1945年の終戦後、日本は連合国との協議の中で戦争を放棄し、軍事力を持たない平和国家として再出発することを決定しました。
憲法第9条では、「戦争の放棄」と「戦力の不保持」が明記され、日本は自衛隊を持ちながらも専守防衛に徹し、積極的に戦争を行わないという平和主義の理念が確立されました。この背景には、広島と長崎の原爆被害や、アジア諸国との関係改善の必要性も影響しています。

基本三原則の影響と現在の課題
「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」は、戦後の日本社会とその政治体制の基礎を築き、現在も重要な意義を持っています。
しかし、現代においてはこれらの原則が抱える課題や変化も議論されています。
以下にそれぞれの三原則がどのように影響しているか、また現在直面している課題について説明します。
国民主権の影響と課題
【影響】
国民主権は、日本の民主主義を支える基本的な理念です。選挙によって国民が代表を選出し、政治に参加できる仕組みが確立されています。これは、戦前の「天皇主権」とは根本的に異なり、国民が主権を行使する民主的な社会を形成する土台となっています。
【課題】
現在、選挙における投票率の低下が問題となっています。特に若年層の投票率が低く、政治への関心が薄れつつあるという懸念があります。
また、政治への信頼の低下や、一部の利益団体や政治家による既得権益の維持も、真の国民主権を実現する上での課題とされています。
これに対し、若者の政治参加を促すための教育や、政治の透明性を高めるための取り組みが必要とされています。
※関連記事:若者の選挙の投票率推移:投票率の変化と内閣支持率・政党支持率の関係について
基本的人権の尊重の影響と課題
【影響】
基本的人権の尊重は、日本が国際社会で尊重される人権基準を満たすために重要な役割を果たしています。
例えば、労働基本権、平等権、表現の自由などが法的に保護されており、これにより国民が安心して生活できる基盤が形成されています。
【課題】
人権に関しては、新しい課題も出現しています。例えば、インターネット上のプライバシーの保護や、差別やヘイトスピーチの問題が挙げられます。
また、日本国内でのジェンダー平等やLGBTQ+の権利保護については、未解決の問題も多く、国際的な基準に達していないと指摘されています。こうした新しい人権問題に対応するためには、法改正や社会的な理解の促進が求められています。
なお、表現の自由とヘイトスピーチとの関係について、以下の記事で詳しく解説しています。
※関連記事:表現の自由とは?その定義・範囲や、ヘイトスピーチ・ネット上の誹謗中傷など現代の課題を徹底解説
平和主義の影響と課題
【影響】
平和主義は、日本が戦後一貫して軍事的行動を抑制し、国際紛争の平和的解決を目指す姿勢を示すものです。これは、特に憲法第9条の「戦争放棄」と「戦力の不保持」によって、日本が自衛以外の軍事的関与を避けてきたことが表れています。
平和主義を掲げることで、国際社会において「平和国家」としての日本のイメージ形成にもつながっています。
【課題】
近年、東アジアの安全保障環境が変化する中で、平和主義に関する議論が活発化しています。特に、北朝鮮のミサイル発射や中国の軍事的な影響力の増大が、日本の安全保障に直接的な影響を与えています。
このため、日本が自衛隊の役割をどのように位置づけるべきかや、集団的自衛権の行使範囲についての議論が行われています。これに対し、憲法第9条をどのように解釈・運用するかが重要な課題となっています。
平和主義について海外の憲法との比較
日本国憲法における「平和主義」は、その独自の特徴として特に憲法第9条に明記されており、戦争の放棄と戦力の不保持を明確にしています。
平和主義は、日本が第二次世界大戦後に選択した重要な政治的原則であり、国際的にも注目されています。
以下では、日本の平和主義を他国の憲法と比較し、その特徴を明らかにします。
参考:国立国会図書館
日本国憲法の平和主義
日本国憲法第9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、戦争の放棄を宣言」し、「陸海空のいかなる戦力も保持しない」としています。
これは、国家としての軍事的な攻撃能力を持たないことを明示しており、日本が自衛権を持つことを前提としながらも、攻撃的な戦争を放棄することを約束しています。
この点が、日本の憲法の最も大きな特徴の一つといえるでしょう。
他国の平和主義的規定との比較
他国の憲法も平和に関する規定を持っていますが、日本のアプローチは特異です。
ドイツの憲法(基本法第26条)では、戦争を「国際法の枠組みの中で行う」と明記しており、戦争を防ぐための努力を重視しています。ドイツも戦後の平和主義を掲げていますが、国際的な軍事行動を認める文脈が含まれています。
イタリアの憲法(第11条)は、「戦争を他国に対しての侵略として禁止」し、国際的な協力による平和を推進することを規定しています。ここでも、国際的な軍事活動が容認されています。
スイスの憲法も「武力行使は国際法に従って行う」ことを示しており、特に中立政策をとっているため、軍事行動を持たない一方で、自衛的な立場を取ることが明記されています。
日本の平和主義の特徴
これらの国々と比較すると、日本の平和主義は以下の点で際立っています。
戦争の放棄の明示性
日本国憲法第9条は、戦争を放棄することを法的に明記している点が特徴的です。他国の憲法は、一般的に国際法に基づいた平和維持を重視しているのに対し、日本は自らの戦争行為を一切排除する姿勢を示しています。
軍事力の不保持
日本は、実質的に軍事力を保持しないことを憲法に盛り込んでおり、これにより自衛隊の役割や位置づけについても独自の議論を引き起こしています。他国は、国防のための軍事力を持つことが一般的であり、これが日本との大きな違いです。
戦後の影響
日本は、第二次世界大戦の教訓を受けて、戦争による被害の回避を徹底する方針をとっています。この背景には、戦争の悲劇を二度と繰り返さないための強い意志があり、平和主義は国民の広範な合意によって支えられています。
まとめ
日本国憲法の三原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は、戦後の日本における政治の基盤を形成しています。国際人権規約との関連を見ながら、これらの原則がどのように国際的な人権の流れとリンクしているかを理解することが重要です。
また、平和主義は他国の憲法と比較しても特徴的であり、これが日本の特異性を強調しています。
現在の課題を踏まえ、三原則の意義を再確認することが求められています。

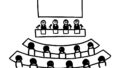

コメント