衆議院の優越とはどのような内容で、何のために認められているのかをまとめました。
※関連記事:政治家の税金事情:納税義務はない?源泉徴収されてる?政治家が税金を優遇されている理由を解説
衆議院の優越とは
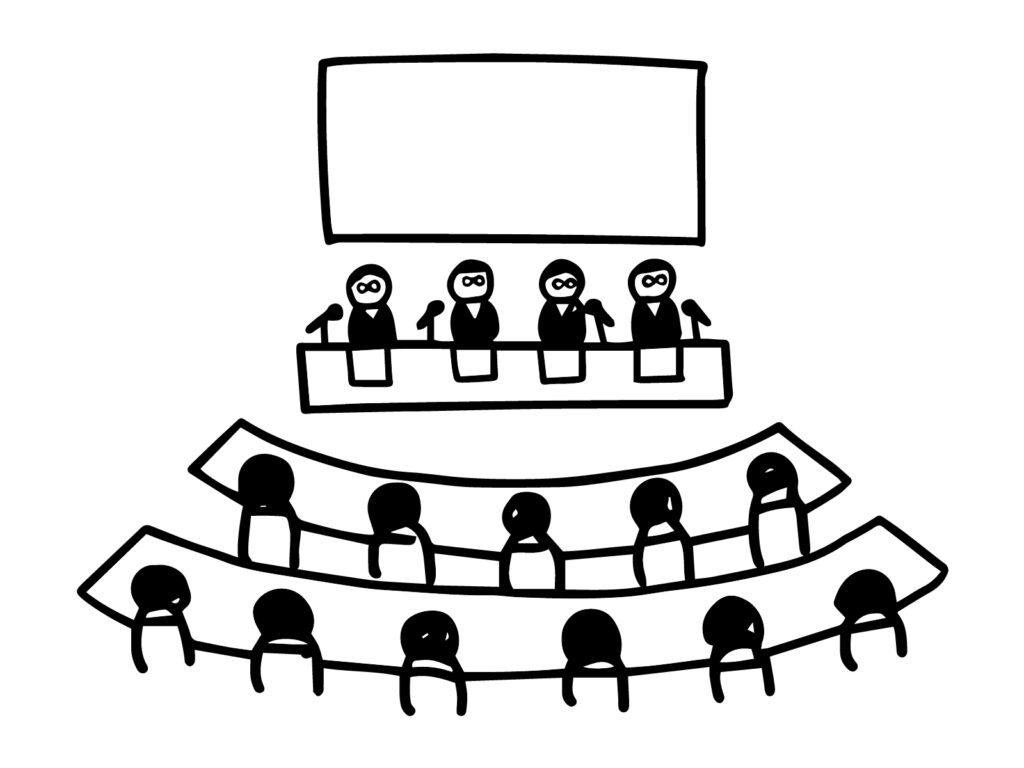
国会は衆議院と参議院に分かれています。そのうち、いくつかの事項については衆議院の意志が優先されます。これを「衆議院の優越」と呼びます。
衆議院の優越が認められているのは、憲法上の優越6つと国会法上の優越3つです。
憲法上の優越6つ
法律案の再議決
国会に法案が提出されると、衆議院→参議院の順に採決が行われます。衆議院で可決された法案が参議院で否決されると、衆議院に戻されます。
このとき、衆議院で3分の2以上の賛成を得られると、この法案は可決されます(憲法59条2項)。参議院で否決されても衆議院単独で法律を成立させられるのです。
※関連記事:議員立法とは:議員立法の手続きや特徴、成立する議員立法が少ない理由を解説
予算先議権
国会の重要な仕事の1つに国家予算の決定があります。内閣が提出した予算案の議決は、衆議院で先に行われます(憲法60条)。その分、予算案の内容に衆議院議員の意見が反映されたものになるのです。
予算案の議決
衆議院を通過した予算案が参議院で30日以内に議決されなかった場合、その予算案で最終決定されます(憲法60条2項)。
つまり、参議院の意見がまとまらないなら衆議院の意見で予算を決めて良いというわけです。
条約の承認
内閣が外交と結んだ条約も、国会で承認されなければ発効できません。条約の承認についても、衆議院と参議院で意見がまとまらないときは衆議院の意見が最終決定になります(憲法61条)。
内閣総理大臣の指名
内閣総理大臣は衆議院・参議院の両方から1名ずつ指名されます。両院から指名された人物が違っていても、衆議院側が指名変更しない限り衆議院で指名された人物が内閣総理大臣になります(憲法67条2項)。
※関連記事:歴代内閣の最低支持率ランキング:歴代総理のワースト支持率とその理由(不祥事など)を紹介
内閣不信任決議権
国会は内閣に対して不信任決議ができます。その権利を持っているのは衆議院だけです(憲法69条)。
不信任決議が可決されると、内閣は10日以内に総辞職するか衆議院を解散して総選挙を実施する必要があります。
内閣不信任決議については、以下の記事で詳しく解説しています。
内閣不信任決議:不信任決議が可決された日本の歴代内閣4つとその経緯を紹介
国会法上の優越3つ
国会会期の延長
通常国会(常会)は年1回1月中に150日間ひらかれます。衆議院と参議院の両院協議会の話し合いによって、1回だけ延長が可能です。
両院協議会で議決が分かれた場合は、衆議院の議決が優先されます(国会法第12条)。
臨時会・特別会の会期延長
常会以外に、内閣が必要と感じて召集する臨時会や、衆議院選挙の後に開かれる特別国会では延長が2回まで可能です。
こちらも、両院協議会で議決が分かれた場合は、衆議院の議決が優先されます(国会法第12条)。
両院協議会の開催請求
衆議院と参議院で法案の議決が異なる場合には、両院から代表者が集まって会議を行う「両院協議会」が開かれます。この両院協議会の開催を請求できるのは衆議院だけです。参議院はこの請求を拒否できません(国会法第84条)。
なお、法案の議決以外に以下の3つの場合には両院協議会を開くことが義務付けられています。
前述のように、これら3つで衆議院の優越が認められています。
※関連記事:国会の日程:国会ではいつ・何の議題が話し合われているのか?国会議員はどんなスケジュールで動いている?
衆議院に強い権限が認められている理由
衆議院に優越が認められているのには理由があります。それは、「政治を停滞させないため」です。
予算の議決、内閣総理大臣の指名、条約の承認といった重要事項が決まらないと、国政が停滞してしまいます。そのため、一方の院に対して優越が認められているのです。
なかでも、衆議院に優越が認められているのには以下のような理由からです。
衆議院のほうが任期は短い
衆議院と参議院では任期が異なっており、衆議院のほうが短いです。
任期が短いほうが「最新の民意」を国会の意思決定に反映させやすいと考えられています。
衆議院には解散がある
さらに、衆議院には解散制度があります。衆議院で内閣不信任案が可決されると、内閣は衆議院を解散して総選挙を行うことができます。
つまり、衆議院が内閣を総辞職させても、内閣は選挙で国民の信を問うことで最新の民意を内閣や国会議員に反映させられるのです。
解散は参議院にはないため、衆議院に優越が認められます。
また、参議院は本当に必要ならば国民の意思に反することも実施できるため、「良識の府」と呼ばれます。
※関連記事:衆議院の解散はなぜやるのか?:郵政解散やハプニング解散などの実例を上げながら解説します
実際には衆議院と参議院は対等
これまで説明してきたように、衆議院は参議院よりもいくつかの点で優越が認められています。
ですが、実際には衆議院と参議院はほぼ対等な関係にあります。
その理由は、「再可決の条件の厳しさ」にあります。
衆議院で可決された法案が参議院で否決されても、衆議院で再度可決されれば法案成立です。ですが、再度可決されるには衆議院で3分の2以上の賛成が必要です。
与党は政権を安定的に運営するために「過半数の議席」を獲得していることがほとんどです。1つの政党で過半数に足りない場合はほかの政党と協力して連立与党となります。
3分の2以上となると、過半数よりはるかにハードルがあがるため、与党だけではなく野党からも一部賛成票を獲得しないといけなくなります。
与党だけで3分2以上になることはめったにないため、それだけの議席数を獲得できると「絶対安定多数」と呼ばれます。
また、衆議院で可決された法案について参議院で60日以内に結論が出ない場合、否決されたと見なされます。通常国会150日のうち60日間も過ぎてしまうと、再度衆議院で審議・採決する時間が足りなくなります。
そこで、法案を実質的に廃案に持っていくために参議院が60日間ぎりぎりまで結論を出さない場合もあります。
また、過去には衆議院解散後に参議院を緊急招集して予算案を可決した内閣もありました。
参議院の緊急集会について以下の記事で詳しく解説しています。
参議院の緊急集会とは?いつ召集されて何を話し合うのか?過去の召集事例2つを紹介
憲法改正には衆議院の優越はない
予算案、法案、内閣総理大臣の指名など、多くの点で衆議院の優越が認められていますが、憲法改正の発議に関しては衆議院の優越はありません。参議院と対等です。
憲法改正はまず、衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成で改正案が発議されます。つづいて衆参各議院での憲法審査会で審査されて、本会議で衆・参議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要です。
このときには参議院で否決されても衆議院で可決されれば…といった優越はありません。
それだけ重要であり、決定スピードよりも審議のハードルに重きが置かれているのです。
なお、国会本会議で憲法改正案が可決されても、最終的に国民投票も行われます。
衆議院の優越が生まれた理由を探る
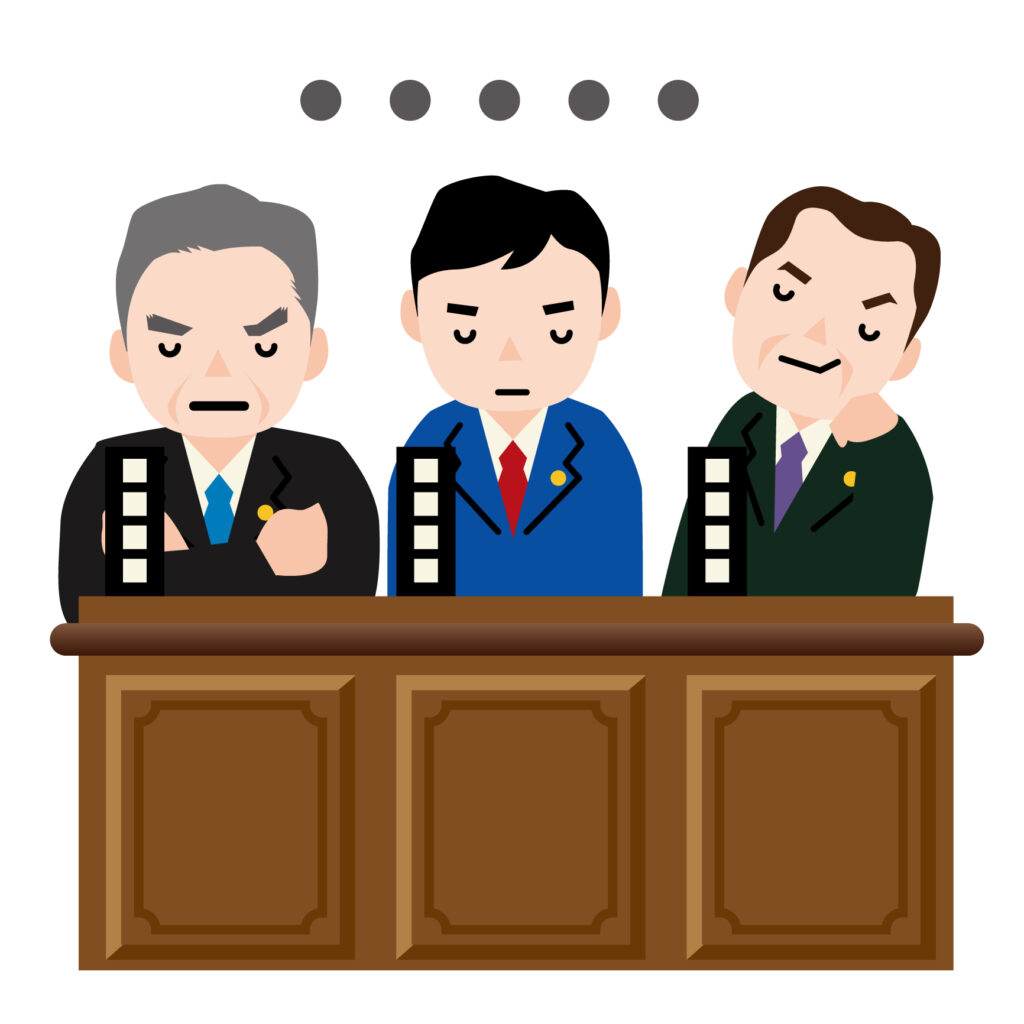
日本国憲法における二院制の仕組み
日本国憲法は、民主主義と効率的な国政運営を両立させるために二院制を採用しています。この二院制は、国会を衆議院と参議院の2つの議院で構成する仕組みで、それぞれ異なる役割と機能を持っています。
衆議院は国民の直接選挙によって選ばれる議員で構成され、解散制度を通じて選挙による国民の意思を素早く反映できる特徴があります。
一方、参議院は長期的な視野で政策を検討する役割を担っています。
衆議院:国民の意思を素早く反映できる
参議院:長期的な視野で政策を検討できる
しかし、日本国憲法では、緊急時や政策の迅速な決定を重視するため、衆議院に予算の先議権や法律案の再議決権など、参議院より優越した権限を与えています。
これにより、衆議院は即時的な意思決定機関としての役割を果たしています。
国民の代表性と解散制度の関係
衆議院の優越の背景には、国民の代表性と解散制度が深く関わっています。
衆議院は国民の直接選挙によって選ばれるため、国民の声をより忠実に反映します。また、衆議院には任期が4年と比較的短く、解散が可能という特徴があるため、社会や政治状況の変化に応じて新しい民意を反映する仕組みが整っています。
一方、参議院は任期6年で解散がなく、3年ごとに半数が改選される仕組みです。この安定性は長期的な視野に基づく政策審議に向いているものの、衆議院ほど迅速に国民の意見を反映することは難しいといえます。
この違いが、衆議院に対する優越性を憲法上認める根拠の1つとなっています。
衆議院の優越が与える影響と課題

政治の安定に与えるプラスの影響
衆議院の優越は、政策決定を迅速化し、政治の安定に大きく寄与しています。特に予算案や法律案の成立を参議院が拒否した場合でも、衆議院で再議決すれば早期に成立させられます。
また、内閣総理大臣の指名でも衆議院の決定が優越するため、迅速に内閣を構成し、政策を実行に移せる体制が整っています。
議会の対立や行き詰まりが長期化することを防ぎ、国民生活に必要な政策が滞るリスクを軽減できます。
衆議院の優越が招く弊害と批判
一方で、衆議院の権限が強すぎる点には批判もあります。
例えば、衆議院が再議決権を行使する場合、参議院の意見が無視される可能性があります。これにより、慎重な政策審議が軽視され、短期的な人気取りの政策が優先される恐れがあります。
また、与党が多数を占める場合、衆議院が事実上行政府の意向をそのまま反映する「追認機関」と化すリスクも指摘されています。
このような構造的課題は、二院制の本来の目的である「多角的な政策審議」と「均衡」を損なう可能性があります。
「衆議院の優越」で政権運営が左右された内閣の実例
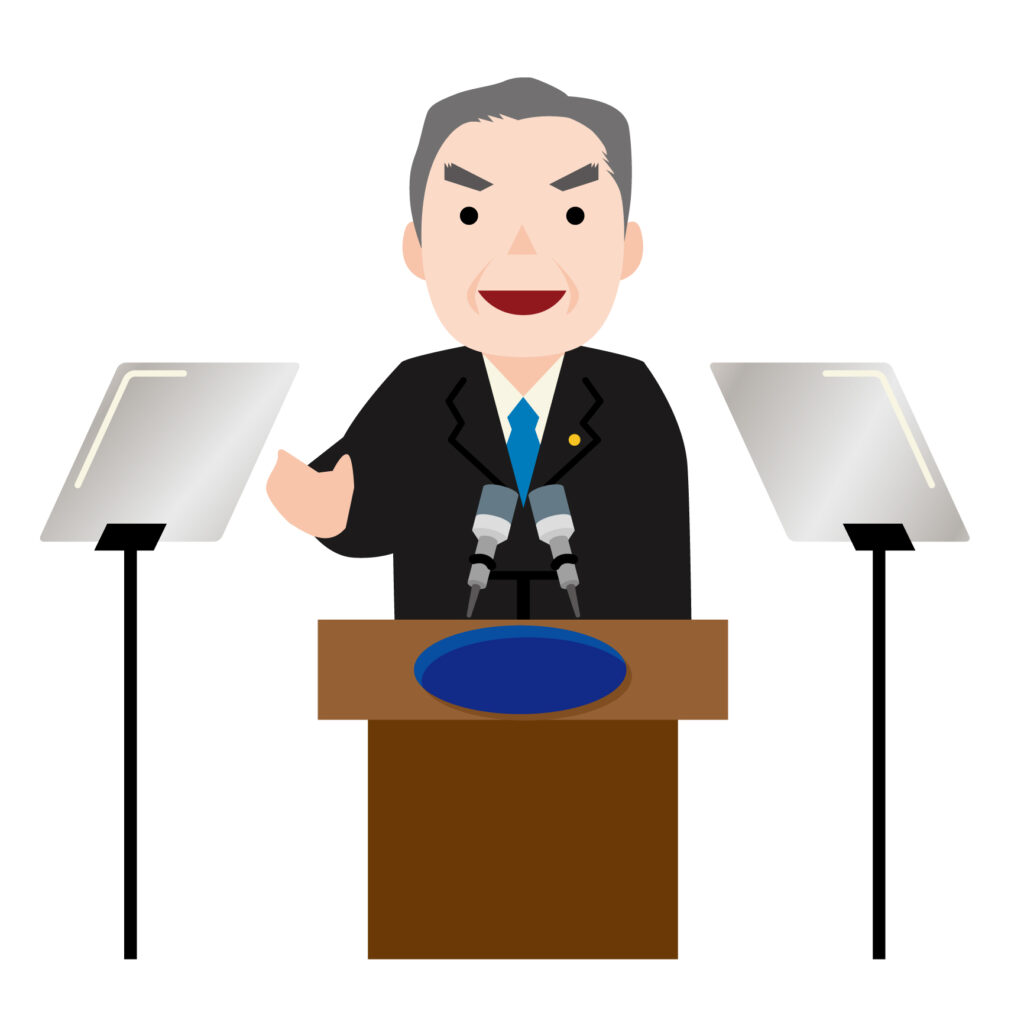
吉田茂内閣(第五次内閣)と単独与党運営の困難
吉田茂内閣は1953年の総選挙後、衆議院で与党自由党が単独過半数を維持しましたが、参議院では過半数を持たず、法案が参議院で否決される事態が頻発しました。
このとき、「衆議院の優越」を利用し、重要法案を再議決して成立させましたが、参議院での審議の停滞や野党の反発が続き、政権運営は困難を極めました。
田中角栄内閣と金権政治批判
1974年の田中角栄内閣では、「金権政治」に対する批判が高まり、衆議院では与党が優越を保ち政策を推進しましたが、参議院での審議過程では野党が厳しい追及を行いました。
田中内閣は衆議院の多数を利用して政権を維持しましたが、国民の批判や参議院での混乱が引き金となり、最終的には退陣に追い込まれました。
この事件が契機となって政治資金規正法が改正されるようになりました。政治資金規正法について以下の記事で詳しく解説しています。
政治資金規正法とは:政治資金スキャンダルと歴代内閣への影響、政治資金規正法改正の内容をまとめました
小泉純一郎内閣と郵政民営化法案
小泉内閣(2001~2006年)は、郵政民営化を進める中で衆議院の優越を活用しました。郵政民営化法案は参議院で否決されましたが、衆議院の優越による再議決で成立させました。
この一件は、衆議院の強い権限が政策を迅速に進めることを示した一方で、参議院の存在意義を問う声を招きました。
また、この過程で党内反対派を公認から排除する「刺客」作戦を実施し、政権運営の強さを印象づけました。
菅直人内閣とねじれ国会
2010年の菅直人内閣では、参議院選挙で与党が過半数を失い「ねじれ国会」が発生しました。
衆議院での優越を利用し予算関連法案の成立を図りましたが、参議院での野党の強硬姿勢により国会運営が停滞。特に重要法案が参議院で否決されるたびに再議決を行う必要があり、政権運営に多大な困難をもたらしました。
安倍晋三内閣(第一次内閣)と辞任の要因
第一次安倍政権(2006~2007年)では、参議院選挙で与党が大敗し、「ねじれ国会」に突入しました。衆議院の優越を活用しつつも、重要法案の成立には苦労しました。
特に参議院での審議停滞や批判が政権支持率の低下につながり、安倍首相は1年で辞任を余儀なくされました。
他国の二院制との比較から見る衆議院の優越
アメリカやイギリスの二院制との違い
アメリカやイギリスの二院制は、日本の二院制とは異なる特徴を持っています。
アメリカでは上院と下院が対等な権限を持ち、それぞれが独立して法案を審議するため、上下院の調整が必須です。イギリスでは下院が優越しますが、上院には法案を見直す役割が与えられ、一定の歯止めをかける仕組みが存在します。
一方、日本では衆議院が参議院より圧倒的に優越しており、特に再議決権や予算の先議権といった機能によって、参議院の影響力が制限されています。
他国と比較すると、日本の二院制はバランスの面で課題があるといえます。
日本の二院制の特徴と課題
日本の二院制は、衆議院と参議院が異なる役割を担うことを前提としていますが、実際には衆議院の優越性が際立っています。このため、参議院の存在意義が問われる場面も少なくありません。
他国と比較した場合、日本の二院制は「迅速性」には優れていますが、「慎重さ」や「多様な意見の反映」という点では劣るといえます。
この課題を解決するためには、参議院の役割を強化し、衆議院との均衡を図る改革が必要です。
衆議院の優越を巡る今後の課題と展望
二院制の役割を再評価する必要性
現在の衆議院優越の仕組みを維持しつつも、参議院の役割を再評価することが重要です。
参議院は、長期的な視点で政策を検討し、衆議院の決定を見直す「熟議の府」として機能するべきですが、現在その役割は十分に果たされていません。このため、参議院の権限強化や独自の役割設定など、二院制全体の在り方を見直す必要があります。
また、衆議院と参議院の役割分担を明確にし、バランスの取れた国会運営を目指す議論を進めることが求められます。
国会改革が目指すべき方向性
国会改革では、衆議院と参議院の役割と権限を見直し、より効果的な国会運営を目指すことが重要です。
例えば、参議院に対して法案審議の強化や、独自の立法提案権を充実させる制度を導入することで、衆議院の決定を補完・監視する機能を高めることが考えられます。
また、国会議員に対する専門知識のサポート体制を強化し、議員個人の立法能力を向上させる取り組みも重要です。
これにより、衆議院優越の仕組みを維持しながら、より健全な国会運営を実現できます。
衆議院の優越に関するQ&A
Q1: 衆議院の優越とは何ですか?
A: 衆議院の優越とは、日本国憲法が定める仕組みで、衆議院が参議院よりも優先的な権限を持つことを指します。具体的には、予算の先議権や法律案の再議決権、内閣総理大臣の指名における優越が含まれます。この仕組みは、衆議院が国民の意思を迅速に反映し、政策決定の停滞を防ぐために設けられています。
Q2: 衆議院が優越する理由は何ですか?
A: 衆議院の優越が設けられた理由は、以下の2点です。
- 国民の代表性: 衆議院議員は国民の直接選挙によって選ばれるため、国民の意思をより強く反映しています。
- 解散制度: 衆議院は解散が可能で、社会や政治状況の変化に応じて新しい民意を迅速に反映できる仕組みがあります。これらにより、政策決定の迅速化が期待されています。
Q3: 衆議院の優越によるメリットは何ですか?
A: 衆議院の優越には以下のメリットがあります。
- 政策決定の迅速化: 予算や重要な法律の成立がスムーズに行えるため、政治の停滞を防ぎます。
- 政治の安定化: 衆議院が主導権を持つことで、与党が明確な方針で政策を実行しやすくなります。
- 緊急時への対応: 迅速な意思決定が可能なため、危機的状況にも柔軟に対応できます。
Q4: 衆議院の優越にはどのようなデメリットがありますか?
A: 衆議院の優越には以下のデメリットも存在します。
- 参議院の役割軽視: 参議院が衆議院の再議決で覆されることが多く、その存在意義が薄れる可能性があります。
- 短期的な政策優先: 衆議院が解散や選挙を意識し、短期的な人気取り政策に偏るリスクがあります。
- 与党の影響力が強すぎる: 衆議院の多数派が与党の場合、与党の意思がそのまま国政に反映されやすく、慎重な政策審議が不足する可能性があります。
Q5: 他国の二院制と日本の衆議院優越はどのように異なりますか?
A: 他国と日本の二院制には以下の違いがあります。
- アメリカ: 上院と下院が対等な権限を持ち、それぞれ独立して法案を審議します。上下院の合意が必要なため、バランスが取れています。
- イギリス: 下院が優越しますが、上院は法案の見直しや遅延措置を通じて重要な歯止めをかけます。
- 日本: 衆議院が再議決権や予算の先議権など、参議院に比べて圧倒的に優越しています。このため、他国よりも上下院のバランスが欠けていると指摘されています。
Q6: 衆議院の優越を巡る課題と今後の展望は?
A: 衆議院の優越には次の課題と改善の展望があります。
- 課題
- 参議院の役割を強化し、慎重な政策審議を促進する必要があります。
- 衆議院の多数派が政策を強行するリスクを抑えるため、参議院の権限を見直すべきです。
- 展望
- 二院制のバランスを再評価し、衆議院と参議院の機能をより明確に分担する改革が求められます。
- 参議院の独自性を高めることで、多角的な政策決定が可能となり、国民の信頼も向上するでしょう。
まとめ
衆議院の優越の内容についてまとめました。
国政を停滞させないため、憲法上の優越6つ(予算先議権、内閣総理大臣の指名など)、国会法上の優越3つが衆議院に認められています。衆議院には解散があるので民意が反映されやすいという特徴があります。
ただし、実際には衆議院と参議院はほぼ対等です。
国政を左右する重要な決定ですから、スピードだけでなく慎重な審議も重視される内容になっています。



コメント